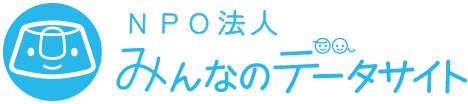第1期 原子力災害に備えるための実戦体験学習講座
第1回「原子力災害に備えるための実践体験学習 講座」の実施報告
原子力災害から命と健康を守るために必要な知識と技術、そして実習での体験を得る実践学習講座の第1回を今年2月から3月まで実施しました。オンラインで4回(8コマ)実施した基礎学習には全国また海外から14人が参加、そのうちの8名が実地研修まで参加しました。
放射線と放射性物質の基礎知識や測定法、被ばく防護法などを学び、原子力災害被災地での実践研修を通じて測定技術の習得と被ばく防護への対応力を身につけたリーダー的人材の育成を目的としています。3月22日(土)〜23日(日)の実地研修を中心に報告します。(文責:大沼淳一)
【1日目】
帰還困難区域・浪江町津島地区「何もしなければ100年は帰れない」地 津島地区へ
郡山駅で集合し、事務局清水の運転するマイクロバスで1時間、津島地区へ。
津島地区の面積は95.5km2(手線の内側の約1.5倍)で、約450世帯・1,400人が暮らしていました。原発事故時の高濃度放射能のため帰還困難区域とされました。2023年3月に特定再生復興拠点区域として整備(除染)、地区のわずか1.6%にあたる153haが規制解除され、復興住宅10棟ができ、現在10世帯が入居しているとのこと。残る98.4%は未だ帰還困難区域で、その一部は特定帰還居住区域として「帰りたい」人がいればその場所だけ除染されるとのこと、未だ全体の計画は示されません。
「ふるさとを返せ 津島原発訴訟」原告団長 今野秀則さんをガイドに講義と見学
津島は、原発が爆発して浜通りの人々が避難してきて1000人ほどの集落に1万人ほどが集中したそう。体育館などの避難施設では足りなくて、多くの民家にも分宿したそうです。懸命に炊き出しなどをして避難者のお世話をしていたのですが、原発が次々と爆発し、高濃度の放射性プルームが襲来した15日に、支所の会議室に集合した馬場浪江町長以下のメンバーが、さらに西の二本松市への再避難を決断したそうです。政府や東電からは何の情報も来ず、テレビ等をみて決めたそうです。
津島でもさらに線量が高いのが赤宇木地区です。事故当時、赤宇木地区の空間線量が異常に高くて、当時名古屋でTVを見ながら心配していたところです。現在でも帰還困難区域のままです。現在Cラボの机の上にある分厚い資料集「100年後の子孫たちへ」は、この赤宇木の人々が制作しました。その編集メンバーのおひとりである今野邦彦さん、そして「津島訴訟」原告団長の今野秀則さんが津島活性化センターの玄関で待っていてくれました。津島訴訟の柱は、賠償と津島の元通りの回復でした。仙台地裁判決では東電と国の責任を認めて賠償せよでしたが、津島を元通りにせよの訴えにはゼロ回答でした。そのため、現在は仙台高裁で控訴審が続いています。
昼食後に、今野秀則さんから津島の歴史や汚染の現況、津島訴訟のことなど熱の入った解説が1時間半ほど続きました。そのあと、クリーニングセンターで防護服に着替えてから、秀則さんに津島地区の案内をしていただきました。津島診療所の前では、浜通りの避難者が押し寄せたときに、持病を抱えた人々や体調不良の人々が診療所の前に長い列を作ったこと、その診察に当たった医師は3日間連続して診療所の中にいたにもかかわらずかなりの被ばくをしていたことが後の積算線量計の記録から判明したこと、ということは診療所の前に並んだ避難者たちは襲来した放射性プルームでかなりの被ばくをしたに違いないという話を聞きました。
阿武隈山地の中ほどに開けた津島の風景は素晴らしく、放射能汚染さえなければ今でも四季折々の山の恵に調和した穏やかな生業が続いていたことでしょう。江戸時代以来のクヌギとコナラの薪炭林、戦後のエネルギー転換でシイタケ原木林として生き延びた山々にも大量の放射能が降り注ぎ、生業の場ではなくなっています。しかも、森林は除染対象ではないので、100年後を待つしかありません。
夕方、クリーンセンターに戻って防護服を脱ぎ、積算線量計の読み取りをした結果シートをもらって津島の現地研修は終了し、宿泊先の南相馬市小高区の双葉屋さんに向かいました。この国道は通行できるものの、両側は全て帰還困難区域であり、車内でも線量計は高い値を示し続けました。
双葉屋さんは、南相馬市の「とどけ鳥」放射能測定所を支えてきた小林岳則さん・とも子さん夫妻が営む宿で、脱原発、反原発の旅人が泊まる拠点になっています。その岳則さんが昨年亡くなってしまい、今ではとも子さんが一人で頑張っています。夕食後は、「俺たちの伝承館」の中筋純さんらが来てくれて、大盛り上がりの交流会が夜中の12時まで続きました。
【2日目】
小高の市民放射能測定室「とどけ鳥」と、おれたちの伝承館見学。大野駅。
翌日はまず、「おれたちの伝承館」(おれ伝)と、同じ敷地に移転した「とどけ鳥」測定所を見学しました。おれ伝には新たに図書室も設けられていました。子ども脱被ばく裁判原告団長の今野寿美男さんに館内案内をしていただき、中筋さんには今はもうなくなってしまった大熊町のストリートビュー(7メートルもある目抜き通りのまちなみ写真)を見せてもらいました。「とどけ鳥」は原発労働者だった経験のある白髭幸雄さんが測定を引き継いでいます。1日目に赤宇木で採取した土壌を測ってもらうと、2万Bq/kgでした。おれ伝の軒先を借りて、空間線量計などの機種や何を測っているかの学習もしました。
次いで訪問したのが、震災遺構として残された請戸小学校です。1階はめちゃめちゃに破壊された教室が津波の威力を伝えます。2階に展示されている写真等で当時の様子がわかります。大津波が入道雲のように松林の向こうに見える写真には寒気がしました。津波が襲ってきたとき、授業中だった子どもたちと先生は、全速力で大平山まで走って助かったのだそうです。津波の到達点、浜辺からの距離など考えると本当に奇跡に思えます。請戸地区は津波の救助が原発の非常事態宣言により打ち切らざるを得なくなり、声が聞こえたのに助けられなかったという悲しい事実もあります。「原発事故さえなければ・・・」もっと助かった命もあったはずです。
続いて双葉町にある「東日本大震災原子力災害伝承館」を見学後、大熊町の大野駅近くに建った豪華な公共施設「クレヴァ大熊」に行ってみると、テレビアニメ「プリキュア」のコスチュームをまとった3人組のイベント開催中で、若い子連れのファミリーが握手を求めて列を作っていました。大熊町や双葉町では元住民の帰還者がほとんどいないかわりに、200万円ほどの補助金で誘われた若い移住者が増えているとの報道もあり、その実態の一部なのかもしれません。なお、「クレヴァ大熊」の1階は除染土壌の中間貯蔵施設を運営管理するJESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)のショウルームになっていて、除染土壌再生利用の安全キャンペーンを展開していました。
大熊町立「学び舎ゆめの森」は0〜15歳までが遊び・学ぶ学校で、大変立派な施設ですが、その周辺の林の線量は高いままです。周辺に生えている「土筆」をみんなで採取し持ち帰り測定することにしました。
全てのプログラムを無事消化して、バスの中で参加者の感想を聴きながら一路郡山駅へ。この研修はぜひ今後も続けてほしい、多くの方に参加してもらいたいという感想をいただきました。
研修中は、線量を測定し、2日間の被ばく量を推計することと研修レポートを書くことが課題。この課題の提出と口頭試験を経て、第1期 みんなのデータサイト「原子力災害被ばく防護士」が誕生します。
第2回の研修に興味がある方は、事務局(minnanods@gmail.com)まで、【ひばく防護士講座希望】と書いてお問い合わせください。次回の日程が決まりましたら詳細をご案内させていただきます。