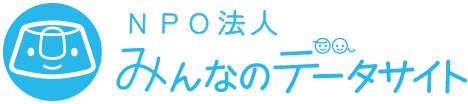【実施報告】原子力防災「放射線被ばく防護士」養成講座 第1期 (2024年7月〜2025年6月)
講座の目的
2011年の福島第一原発事故。あのとき多くの人々が、放射性物質とはなんなのか?単位の意味すらも理解していないひとが多かったと思います。大きな混乱のなか錯綜した情報が飛び交い、何が本当で何は嘘なのかを見分けられなかったかもしれません。災害時にどのように情報が伝達されるのか、されないのか、できないのか、といった混乱も目の当たりにしてきました。
こうした経験をへて私たちは、「自ら知り・判断できる知識と経験を持つこと」がいざというとき被ばくを防ぐこと、命を守る力になると考えました。行政の発信をただ受け身で待つのではなく、自ら判断し、行動できる市民を育てる。
それが、3.11を教訓として未来へ防災意識をつなげることになる。そんな思いから「放射線被ばく防護士」養成講座は始まりました。
▶ 第1期講座の実施概要
| 区分 | 内容 |
| 講座企画・テキスト開発 |
2024年7月〜 |
| 参加者募集 | 2024年11月〜 |
事前基礎学習(オンライン) |
2025年2月1・8・15・22日 19:00-21:00(全8コマ) |
| 実地研修(宿泊型) | 2025年3月22~23日(1泊2日) |
| 参加者数 | 基礎学習:21名/実地研修:8名 |
| 地域分布 | 北海道〜沖縄・フランス含む14都道府県+海外 |
| 修了・認定者数 | 6名が「放射線被ばく防護士」として認定 |
▶ オンライン基礎学習(2025年2月)
全4日間・計8コマにわたる事前講義は、Zoomを用いて全国・海外の参加者21名が受講。放射性物質の性質や放射線の単位、健康影響の基礎から、災害時の判断のポイントまでを体系的に学びました。
各日終了後にはフィードバックアンケート実施、意見をいただきながら理解度が低かった内容や要望に応じて補講も交えて学習を進めました。
▶ 実地研修レポート(2025年3月22–23日)
【1日目】福島県浪江町・津島地区へ
訪問地:帰還困難区域「津島」
第一部)福島県浪江町津島地区 今野秀則さん のお話
福島県浪江町津島地区の行政区長であり、「ふるさとを返せ津島原発訴訟」原告団長でもある今野秀則さんにお話しを聞きました。今野さんは、2011年の東京電力福島第一原発事故により、地元住民としてどのような被害を受けたのか、震災直後の避難者受け入れから一転、全町避難になったこと、裁判のことなどを写真や資料を交えてお話いただきました。
被災の現実と「帰還困難区域」
津島地区は、約450世帯・1,400人が暮らしていた山間の地域ですが、その98%以上が今なお「帰還困難区域」に指定されたままです。除染が行われ帰還ができる「特定再生復興拠点」は地域全体のわずか1.6%にすぎません。住民は、野生動物に荒らされ雨漏り等で傷み自宅の解体をするか、住めないけれど壊すのはどうしても忍びないと残すか、苦渋の決断を迫られました。今野さんは「住民は断腸の思いで壊している」と語り、先祖から引き継いだ多くの立派なお屋敷が獣に荒らされ、木々に呑まれていく様子を写真とともに紹介しました。
「ふるさとを返せ」訴訟の経緯
今野さんは住民約650名(これは地域住民の約半分にあたります)とともに「ふるさとを返せ津島原発訴訟」を提起し、国と東京電力に対し、原状回復と損害賠償を求めています。2021年の福島地裁郡山支部判決では、国・東電の責任は一部認められたものの、原状回復の請求は退けられました。その後、6.17最高裁の判決により、国の責任を問う訴訟はさらに厳しい局面にあるといいます。現在今野さんたちは「不作為」ではなく全電源喪失時の対策を取っていない危険な原発を設置した「作為的加害行為」という新たな視点で、現在も仙台高裁で闘いを続けています。
東日本大震災当日から全町避難まで
東日本大震災当日、津島地区でも強い揺れがあり、揺れるたびに戸外に飛び出すほどでした。ただし建物の損壊は少なく、瓦が落ちたり棚の食器が割れた程度で、能登半島地震のような深刻な被害はありませんでした。
しかし、翌日から状況は大きく変わりました。3月12日以降、沿岸部の被災地から浪江町津島地区に避難者が次々とやってきて、集会所、小中学校、体育館、校庭などすべてが満杯となりました。津島には最大で約1万人とも言われる人々が避難し、道路は車で埋まり、活性化センター周辺には自衛隊や消防、町役場がやってきました。
地元住民は炊き出しやトイレの設置に奔走し、一般の民家でも避難してきた人々を受け入れました。広い農家では1軒で30〜40人を受け入れた例もありました。顔も知らない避難者を受け入れざるを得ない状況で、住民は自給自足の生活資源を使いながら支援にあたりました。
3月15日、町の対策本部は津島からの避難を決定しました。それまでに国や東電から放射能に関する情報はなく、SPEEDIの予測も提供されていませんでした。町長以下は周囲の町が避難している現実を見て「自分たちも避難すべきだ」と独自に判断したのです。
避難命令が出されたあとも、酪農家などは家畜を残しての避難が難しく、一部の住民は5月中旬までとどまりました。基本的には西の二本松市方面に避難しましたが、避難先の具体的な指定はなく、それぞれが自力で移動先を探さざるを得ませんでした。
机上の空論の避難計画についても指摘
今野さんは当時、行政区長であると同時に福島県社会福祉協議会に勤務する立場もありました。双方の立場として事故後に起きた実際を目の当たりにしての、貴重なお話を伺うことができました。
事故直後、津島地区は周辺の避難者1万人近くを受け入れましたが、その数日後には地域全体が避難を余儀なくされました。
原発が爆発した映像や、隣町に呼びかけられている避難のサイレン、でもここ津島には何も連絡がない・・・果たして我々はこのままここにとどまっていていいのか、3月15日の10時から、浪江町災害対策本部会議が開かれ、その場に今野さんは行政区長として参加。 町長以下町の幹部、自衛隊、警察、消防、地域の行政区長、農業委員とか町会議員などが集まり、状況の説明のあと、町長が「避難するしかない」と決断を下したそうです。
それで午後には自分の行政区の全ての世帯(今野さんは50世帯)を1戸1戸訪ねて在宅している人たちに避難を呼びかけました。不在の家が既に避難したのか、たまたま外出しているだけなのかもわからないのでその日は今野さんは奥様とお子さんを先に避難させて、ご自身は自宅に留まり、翌日再度不在だった家も含め全戸を回り、避難を呼びかけたといいます。
また、社協のお立場として、高齢者や障害者を含む住民の避難に多くの困難があることを具体的に教えていただきました。老夫婦で車の運転ができない、寝たきり家族がいる世帯は、幸いにも自衛隊や消防がいたのでお願いして布団の四隅を4人でもって運び、寝たまま搬送できる車を用意してもらって避難したこともあったそう。
またトイレの問題などもあり、身体に障害があるため通常の避難所では過ごせない状態の方々からの相談電話に対応し、受入先を見つけるのも困難を極めたそうです。そもそもどの施設も以前からの入所者に加え避難者もいっぱいいるので、廊下まで溢れかえり足の踏み場もないような状態だったから、と。
このように、避難ひとつとっても、そんなに簡単なことではない、とおっしゃいました。
ほとんど何も持ち出せず着のみ着のままで避難したその後も、避難先を転々とせざるを得ず、大きな負担を強いられた状況についても伺いました。
東日本大震災後、いったん日本にある原発は全て稼働を停止しました。しかし今、再稼働や稼働年数の見直しなど、まるで事故が起きたことなど忘れてしまったかのように原発回帰が進んでいるように感じられます。そのような中、現在の避難計画がいかに現実に即していないかが浮き彫りになったことも語られました。今野さんは事故当時の状況を話しながら「いま、国や自治体が立てている避難計画など絶対に機能しない」と言い切っておられました。
全てが奪われた その全て、とは。
原発事故により、私たちは「ふるさと津島」をまるごと失いました。ここで生まれ育ち、働き、家族を築き、地域の人々と交流しながら暮らしてきた場所です。自然とのつながり、地域の人間関係、農業や山仕事の協力関係、長年続いてきた文化・伝統・芸能など、生活を支えてきたすべてが奪われました。誇りや自尊心、アイデンティティといった精神的な支えまでもが失われてしまいました。
また、地域の家屋の多くは解体されつつあります。今野さん自身の家は残すことを決断したと言いますが、周囲のほとんどの家は取り壊されています。解体を控えた家では、内部の荷物が搬出され、重機による取り壊しの準備が進められているそうです。写真で見せていただいた空撮図でも、解体の順番待ちが多いそうです。
地域の交流を象徴していた行事も途絶えてしまいました。たとえば、住民が資金を出し合い、事前の打ち合わせや子どもたちの練習を経て実施されていた盆踊り、300年続く「田植え踊り」なども、避難による住民の分散と高齢化のために継続が困難となっています。田植え踊りは、現在、一部の若者や大学の協力で継承活動が試みられていますが、多くの地区では事実上実施不可能な状況です。
このように、原発事故は単なる放射能汚染にとどまらず、地域の暮らし、文化、歴史のすべてを奪ってしまいました。
今野さんの言葉からは、14年という長きにわたり被害を受け続ける人々の実情、そして「唯一無二のふるさと」を奪われたことへの怒りと無念を感じました。 本講演は、原子力防災を考える上で「原子力災害とはどのようなものなのか」を受講者が目の当たりにする、貴重な機会となりました。
第二部)津島地区の見学と被ばく防護の実際
今野秀則さんの講演に続いて、私たちは実際に津島の地を案内していただきました。現地に入るのに先立ち、活性化センター近くのスクリーニング場で防護服一式を受け取り、事前に学んでいた着装法を復習しながら着用。積算線量計は代表の3名が装着し、緊張感を抱きながらマイクロバスに乗り込みました。案内は、今野秀則さんと今野邦彦さんのお二人にお願いし、実情を視察しながら 放射線測定の実習も行いました。
実地を訪れ伺ったお話と私たちが実際に見せていただいたこと
バスの乗降の都度、車内の放射能汚染を防止するために靴カバーを取り替えながら、防護服に身を包んで歩きました。そこは、津島地区のわずか1.6%にあたる特定再生復興拠点区域、つまり帰還できるようになったエリア内と、現在も帰還困難区域のままに残されている場所の両方です。そこには更地となった邦彦さんのご自宅跡、今も解体せずに残すと決めた秀則さんの家、集落の心のよりどころだった寺社、開拓の記念碑、そして診療所や学校…。どの場所もかつては人々の暮らしの中心であり、賑わい・暮らしがあった痕跡が残っています。また、わずかに移住してきた方々や帰還した人が庭いじりをしているところも通過しました。その通常の暮らしと、私たちが防護服を着用して完全装備で訪れている状況とのギャップを感じざるを得ませんでした。
各所でとても印象深いお話を伺いましたが、ここでは津島診療所の話をご紹介します。
原発事故翌日の3月12日、避難してきた人たちが体調が悪くなったり持病の薬を求めて地区内にある診療所に200メートルもの列をなしたというお話。郡山から通い、僻地医療に尽力していた関根先生は、地元の看護師さんからの呼び出しを受けてその長蛇の列に応じ、避難者の診察にあたりました。積算線量計を身につけていた先生の、全町避難までの4日間の被ばく線量は800マイクロシーベルトに達したそうです。診療所のコンクリートの建物の中にいた先生がその数字なら、屋外で並んでいた住民やそこに放射能がきていると知らずに外で遊びまわっていた子どもたちは、その何倍もの被ばくをしていたはずだ、と今野さんはおっしゃいました。
被災地を訪れて私たち一人一人が学んだこと
美しい山あいの風景に、線量計のピピピという警告音と、目に見えて針が振れるその動きに、参加者たちは緊張しつつ歩を進めました。無味無臭の放射性物質は、人間の感覚では一切捉えることができない。線量計があって初めて“そこにある”と知る現実。津島を実際に案内していただき、原発事故の被害を目の当たりにすることで、参加者それぞれに 原発事故とは?放射性物質とは?被ばくとは?では、被ばくを防ぐにはどうしたらいいのか?といったことを考える貴重な機会となりました。
ここに暮らしていた人々が避難を余儀なくされ、大切な先祖から引き継いだ屋敷や田畑が荒れ果てて、地域のつながりも失い、誇りもアイデンティティも失われてしまったと語っていた今野さんの思いを忘れずに、この現場を見た私たち自身も また次の方々へ語り継いでいかねばならないと感じました。
貴重なお話を聞かせていただき、また丁寧に案内して解説してくださった今野秀則さん、今野邦彦さんに改めて深くお礼を申し上げます。
夜の交流
見学を終えた私たちは、南相馬市小高の双葉屋旅館へ移動し、夕食を囲みながら参加者同士で感想を語り合いました。言葉にするにはあまりにも重く、簡単には整理できない一日でしたが、それぞれが「津島で見たもの、感じたもの」を共有する時間となりました。
原子力災害が単なる数字や制度の問題ではなく、「人の生活」と「ふるさとの物語」に直結していることを実感させるものでした。この日の経験が災害に備える私たち一人ひとりにとって、かけがえのない学びとなることを願っています。
【2日目】記憶を継ぐ、未来を考える
おれたちの伝承館・とどけ鳥
東日本大震災・福島原発事故の記憶を未来に伝え、語り合える場を目指して南相馬市小高に市民の力で開設された「おれたちの伝承館」では、今野寿美男さんに館内作品をご案内いただきました。
館長の中筋純さんからは、このあと私たちが訪れる予定になっている大熊町の解体前の町の様子を「ストリートビュー」という7メートルもの絵巻物のような写真で見せていただきました。
また昨年、同じ敷地内に移転して新規開設した市民放射能測定所「とどけ鳥」所長の白髭幸雄さんに測定室の見学と測定器などについて解説をしていただきました。
震災遺構・請戸小学校
次に津波震災遺構の「請戸小学校」を見学。校舎の破壊具合から想像される大津波の威力に圧倒されます。それでも1キロも先の小高い山へ走って走って、子どもたちが生き延びることができたという奇跡。一方で津波被災者の捜索は原発事故のせいで中断、助けられなかった命もたくさんあることを改めて胸に刻みました。2階の展示コーナーに様々な資料があります。津波被災も原発事故と無縁では決してないと感じました。

大熊町の復興と現実
クレバ大熊は、駅前に2025年3月にできた新しい施設です。先ほど中筋さんに見せていただいたストリートビューの巻物写真でみた、かつての大熊町の暮らしがどこにどのようにあったのか想像すらつきません。全て取り壊され、土が大きく削られて除染され、道すらも新しく計画整備され、全く新しい街になりつつありました。
折しもオープン記念の「プリキュア・ショー」に、親子連れがたくさん集まっていました。写真では、握手会のために並んでいる人々が小さく写っています。
「学び舎ゆめの森」周辺も見学。真新しい立派な校舎や芝生の庭が印象的です。一方で、そのすぐ隣には今なお高線量の地が存在していました。日曜日で授業はやっていませんが、子どもたちが日常過ごす場所から道一本隔てたところに、いまだこのようなホットスポットが残っているという現実がありました。
現在、避難区域とされていた12市町村への移住促進施策や企業誘致計画など復興再生にまつわる動きは年年加速しています。しかし、ひとたび放射性物質に激甚汚染されてしまった地域の再生は、一筋縄ではいかないという事実を目の当たりにすることとなりました。
これから移住してくる人たちやここで働く方々に対して、行政は都合の良い情報だけを出してはいまいか? 被ばく防護の対策をきちんと伝えていくべきではないか、と感じました。
▶ 修了と今後へ
2日間の研修後、レポートの提出と口頭試問を経て6名が「放射線被ばく防護士」に認定されました。
この資格はゴールではなく「スタート」です。いざというときに異常に気づき、行動し、周囲に説明できる。そんな力を地域に持ち帰って、今後も継続的に学びと行動を重ねていってほしいと願っています。
▶ 参加者の声(抜粋)
「実地研修は衝撃だった、特に津島。原発事故のリアルを知ることができ、自分自身についても考える機会をいただいた」
「原子力災害時の現実を肌で感じた。受け身でなく、市民が自ら判断し行動するリテラシーの必要性を痛感。」
「除染された学校の隣に高線量の林。無念さが胸に迫った。」
「政府の発信では見えない“空白”があることに気づいた。“何を言っているかではなく、何を言っていないか”を見抜く視点が重要。」
「今回この研修に参加できて本当によかった」
「一人でも多くの方にこの研修に参加してもらいたい」
▶ 関係者からのメッセージ
今野秀則さん:
「足を運び、現地を見てくださることに感謝しています。」
今野邦彦さん:
「忘れられること、無かったことにされることが怖い。そして、これはいずれ皆さん自身にも降りかかる問題だということが最もお伝えしたいことです。」
▶ プログラム責任者より(村上直行)
本講座では、座学と実地を通じて放射線や防護の知識を深めただけでなく、被災地の今を“体感”する学びを大切にしました。現場での声を聴き、空気に触れ、見えないものを感じ取る力が育まれたと思います。課題としては、参加者の多様な背景に対する柔軟なサポート体制やフォローアップが必要と感じています。今後もより実効性ある学びの場を目指していきます。
▶ 主催・協力・監修
●この事業は、真如苑さまの 防災減災助成プログラムのご支援をいただいて実施しています
●テキスト監修:東京大学 小豆川勝見助教
●協力:おれたちの伝承館 中筋純さん、今野邦彦さん、今野秀則さん、市民放射能測定室「とどけ鳥」 白髭幸雄さん、ほか多くの皆さま