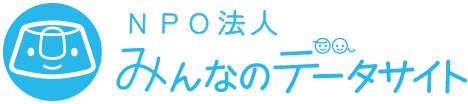新理事長より就任のごあいさつ
今期より理事長を務めます阿部浩美です。
私は2024年4月までNPO法人ふくしま30年プロジェクトに所属し、みんなのデータサイト事務局として関わっておりましたが、ふくしま30年プロジェクトの法人解散に伴い、現在はみんなのデータサイト福島ラボで放射能測定と事務局手伝いを行っています。
私事になりますが、2022年1月に脳出血で倒れ、5カ月ほど入院をしました。
ちょうど退院して、自宅での生活期リハビリに移行したタイミングの2022年6月17日、最高裁判決で福島、群馬、千葉、愛媛で提訴された4件の原発関連裁判について「津波対策が講じられていても事故が発生した可能性が相当ある」として、国の賠償責任はないとする統一判断が示されました。
いま、東京電力福島第一原発事故(以下、第一原発事故)による核災害発災から15年目を迎えようとしています。すでに第一原発事故対応は完了したものというアリバイ作りのように全村・全町避難となっていた自治体の避難が解除されました。強制避難を余儀なくされた放射能汚染の激甚地域が地域再生のスタートラインに立ったと国だけでなく自治体からも喧伝され、社会のなかでも当該事故があたかも終了したこととして位置づけられています。
はたして、第一原発の核災害によって、故郷(資産価値だけではなく地域社会といったコミュニティも含む)を失った人にとっての復興とは何なのでしょうか。
前述しましたように、故郷を失った住民を含む被災者が提訴した裁判について、一審、二審で負けても控訴をし、最終審まで徹底的に争う日本国政府と東電の姿勢からみても、誠意を持っての謝罪はありません。それまでの生活を破壊された憎しみも悲しみも晴らせない被災者にとって、それは苦しく惨めでもあり、干支が一巡しようがその状態は変わっていません。
何故に日本国政府は、核災害の被害にあった住民に対して冷酷なのか? 歴史的に東北は、中央のために人、食料、エネルギーとあらゆるリソースの供給地で、国内における植民地と言っていい立場だったと言われます。また、旧大日本帝国の頃から政府は常に棄民と言える移民、開拓団政策を取っています。旧満州国の満蒙開拓団が典型ですが、国内の食糧需給が賄えないとなると常に人々を故郷の外へと放出してきました。
そして、棄民と記したのは、日本政府が住民に対しての支援を放棄することを厭わないからです。27万人の満蒙開拓団に至っては、旧ソ連の侵攻によって關東軍のみが日本本国に撤収し、住民は見捨てられ自力で逃げることを余儀なくされました。それは、福島第一原発の核災害によって故郷を失った人々の姿と重なって見えます。
強制避難区域は次々と解除され、道路や鉄道を開通させる、新しい役所を建設するなどハード面には無尽蔵に予算がおりて、故郷の風景が変わっていっています。そこにはかつての住民の姿はなく、真新しい庁舎だけが建っているという滑稽な姿があります。
国を舵取る老人たちには、先の戦争による廃墟から復興を果たしたという幻想があるからなのかもしれませんが、このように政府が住民を切り捨ててきた歴史を踏まえれば、第一原発の核災害において、彼らが真の復興と呼べるものを成し遂げることはないのではないかと思います。
それゆえに、私は、第一原発事故による核災害によって故郷を追われた被災者の復興の一助となる活動に邁進する所存です。