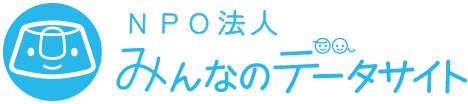「私たちの10年 もりそくスタッフ座談会」
―――森の測定室に携わってきてどんなことを感じている?
まさみ:放射能測定だけではなく子育てや食の学びをこの場所でしてきたね。
ようこ:日常のほんの些細な「こんなこと聞いてみたい」が聞けたり一緒に考えてくれる人がいたから続けてこられたね。
なおみ:放射能に興味関心がない周囲の人との温度差を埋めてくれたし、放射能だけでなく添加物や農薬のことなど他に気がかりなことも気軽に話せたからそこから得たものが多いなぁ。子育ての上で必要な情報が自然と得られる場だよね。
一人で情報を集めたり講演会にいくという方法ではなく、ハードルが下がった状態で勉強ができた。ハードルが低い分すぐに自分の生活に戻れるし。
まさみ:電車に乗って講演会に行って新しいことを知っても、共有できない環境だとそのあとに自分の日常にかみ合わせる作業が必要だけど、この場ならみんなと話しながら考えがまとまったりね。
ようこ:生活の延長上で知りたいことが知れる場だね。安心感がある。
まさみ:日々の生活の出来事に共感してもらえたりアドバイスもらったりね。
なおみ:年齢の違う子どもを持つ親同士、教え合ったり経験済みのことを教えてもらったり。子どもたちの縦のつながりもできたね。
今晩のごはんの話とか、家族、学校、職場、家事、地域問題の話、地域活動をされている方の話を聞いたりして、話題は多岐にわたるね。
ようこ:井戸端会議だよね。
まさみ:お茶請けに手作りのケーキやクッキーもあって。
なおみ:お菓子を作る側としては、重たい話になったら少しでも場がなごむようなものを出せたら、という気持ちでね。
食べ物好きな人が集まっているから、気になったら「測定してみよう」となるし、受け止めるには辛い結果が出てもせめてもの思いを共有してきた。こういう場があるだけで捉え方も変わってくる。測定結果も含めて「食」に関する話を自然にできて循環しているかんじ。
ようこ:放射能測定は環境調査もあるけど、特に森の測定室は食が中心。子育てが軸にあるから「食」とは密接だよね。
なおみ:ここに来なかったら見落としていたこともあった。学校の対応とか。
ようこ:なおみさんもまさみさんもお子さんが小1からここに関わっているけど、これまでここで得たものが子育てにどう作用したのかな?
なおみ:小学校で導入されたフッ素うがいについて知識を深めたり、給食で気を付けることを子どもに伝えたりしたよ。
まさみ:ここがきっかけで自分も気を付けるようになったよ。知らないことばかりだった。
なおみ:玄米を精米してぬかを利用していたけど、ぬかだけを測定してみようと思ったのも知識を得たからだし、きのこ類に放射能が出やすいことも知らなかった。
ようこ:影響が大きいね。
なおみ:同じ地域の子育てママと、ここで出会うのとどこかで出会うのとでは関係も違ったかもなぁ。
ようこ:子育てを助けてくれる場、人とのつながりが生まれる場ということかな。
まさみ:人を思いやる人が多く集まってくる場所だよね。
なおみ:地域支援システムを教えてもらったり。ここに来ると教わるものがたくさんある。
ようこ:日常的に接する人とはまた別の交流ができるんだよね。
なおみ:自分たちの「食」を守りたいという自分たちのニーズで活動してきたけど、自然発生的にコミュニティの場となって、必要な情報を必要な人へ繋いでいくプラットフォームとしての役割を担ってきたと思う。
私たちがここで発信し続けなければならないという気持ちより、温かいご縁が原動力になって自然な形で続いてきたのが森の測定室だね。
まさみ:私にとってここは素直に泣いたり笑ったりできる場だなぁ。改めてこうして考えてみると、このコミュニティに私たちは支えられ、助けられてるってことだ!笑
3人:ほんとにそうだねぇ。