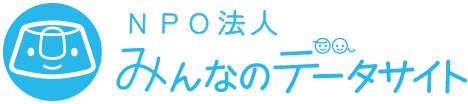Cラボの10年をふりかえる
福島原発事故後10年、新聞各紙がこの10年をふりかえる特集記事を組んでいます。市民運動も10年の節目を意識した企画を考えています。みんなのデータサイトも、事故後10年間に何が起きたのか、市民測定所は何が出来て何が出来なかったのか、市民科学の歴史にどんな足跡を残してきたのかを整理する良い機会ではないかということで、参加する市民測定所から報告を募ろうという呼びかけが運営委員会から発信されました。
これを受けて、Cラボの10年を書いてみることにします。
但し、少々変則なのですが過去に書かれた二つの文章をふりかえってみるところから始めたいと思います。
一つ目は2011年に書かれたもので、C-ラボ発足の意気込みが述べられてます。月刊「むすぶ」489号(2011年10月)に掲載された報告です。意気込み倒れでできなかったことも多々あるし、食品汚染がチェルノブイリ事故と同等レベルを想定して自主基準の設定を試みたりしたことが述べられていますが、この基準はその後ほとんど機能しませんでした。母乳や尿の測定も出来ませんでした。汚染地の支援はそれなりに頑張れたかと思います。
★発足時(2011年)の記録 〜月刊「むすぶ」2011年10月号掲載の報告より〜
市民放射能測定センター 始動!
1.放射能汚染下で生きてゆく
破滅的な事故を起こした福島原発によってばらまかれた放射能の影響は深刻です。なにしろ原発1基が1年間稼働すると、広島原爆1000発分の死の灰ができるのです。絶対に壊れてはいけない圧力容器に穴が開き、融けた死の灰入りの燃料棒が格納容器へと流れ出し、一部は水素爆発とともに外部へと放出されたのです。
食品汚染に限ってみても、野菜類や牛乳汚染に続いて肉牛や海産物の汚染も表面化してきており、この国は長いスパンで放射能汚染をかかえながら進まざるをえないことになってしまいました。木曽川などが流れ込む伊勢三河湾集水域で暮らす私たちは、福島県などと比べればはるかに安全な地域に暮らし、流域自給にこだわれば食品から放射能を取り込む心配は少ないでしょう。
しかし全く心配ないかと言えばそうとも言えません。新城茶から360 Bq/kgの放射性セシウムがでました。宮城県産のワラを与えた飛騨牛の汚染も報告されています。島根県では、福島県から買った牛の糞からつくった堆肥から基準を超える放射性セシウムが出ました。
セシウムCs-137の生物学的半減期は100日程度と短いので、汚染されていない餌を与えれば牛はきれいになっていきますが、物理的半減期が長いので(約30年)、セシウムは物質循環のルートに沿って何度でも人間を含めた生物の体を通り抜けるのです。
海にたれ流された放射能も、同様に沿岸生態系の中で循環を始めています。カツオなどの回遊魚が秋にはその循環の輪から出て南下してくるでしょう。そもそも三陸沖は世界3大漁場に数えられる豊かな水域です。回遊魚以外にもおいしい海産物がたくさん獲れて東海地方にも供給されてきたのです。
2.市民放射能測定センターの構想と立ち上げ
この状況の中で市民、とりわけ放射線感受性の高い子供や妊婦を守るために放射線被曝を出来る限り少なくする必要があります。そのためには、全ての食品の放射能含有量の測定と公表が必要です。
この仕事は本来政府や自治体の仕事であり、その分析費用は東京電力に支払い義務があるはずです。しかし、こうした深刻な事態に至っても政府や自治体の動きは鈍く、生産者も消費者も困惑と不安の中にあります。そこで「未来につなげる・東海ネット」(福島事故後に結成された原発に依存しない社会をめざす緩やかなネットワークです)は、食品中の放射能含有量を測定して市民に情報提供するとともに、地方自治体や政府に測定体制の早急な整備を求めていくために、市民による放射能測定センターを開設することにしました。測定体制が整えば、福島をはじめとする汚染激甚地を支援するための調査や分析を行うことも計画しています。
放射能測定機の代金は約500万円でした。高木仁三郎市民科学基金(核化学者として生涯をかけて原発の危険性を訴え続けられた高木さんが遺されたお金が基になった基金です)から100万円の助成金がいただけることになり、それをタネ銭にして募っている寄付金の集まり具合は順調です。とりあえず借入金で不足分をうめて、測定機は納品されました。現在は、名古屋市西区の産直団体「生活クラブ」に仮設置し、約2カ月のテスト運転を経て9月25日に開所式を行いました。
3.ボランティア測定スタッフの養成
市民ボランティア測定者を大量に養成して、測定シフトを組む予定です。すでに5回の養成講座を行い、合計約60名の受講者がありました。座学と実習で4時間ほどの充実した内容です。この中から20人ほどの皆さんが、すでにシフトに入って測定を行っています。またその中の数名の方は、新しい測定者の指導もできるようになりつつあります。高木仁三郎さんが提唱した市民科学の担い手としての市民科学者養成センターの性格も帯びつつあるともいえるかもしれません。今後も、毎月1回程度、養成講座を開催し、ボランティア測定者100人体制をめざしています。
測定者の主な仕事は、野菜や果物の皮をむいたり芯をとったり、魚の内臓をとったり、細かく刻んだりフードプロセッサーで細かくしたり、まるで台所仕事と同じですが、他のサンプルや測定装置を汚染しないように細心の注意が必要です。こうやって前処理したサンプルを決められた容器に隙間なく充填し、測定装置にかけた後、コンピューターにサンプル重量やサンプルの種別を入力して測定開始ボタンを押します。
得られた結果は、問題がなければプリントアウトされた帳票を読み取り、報告書を作成することになりますが、必ず専門家のチェックが必要です。とりわけ天然に存在するトリウムやウラニウムとその娘核種が混在している土壌のサンプルでは、帳票上の測定値が正しいとは限りません。この種のサンプルに関する測定機の応答について、検討作業を行いつつあります。
4.測定料金
市民が気軽に測ってほしいサンプルを持ち込めるようにするには、測定料金を低く抑えなければなりません。必要経費のうち家賃やスタッフ人件費、光熱費(測定機の特性から空調が必要)などを全く計算せず、えいやっと武家の商法で決めた測定料金は、約90分の測定時間を要する1核種当たりの検出限界10 Bq/kgで2000円、350分測定の5 Bq/kgで4000円です。
検出限界を低いところまで測ろうとすれば、サンプル量を増やすか測定時間を長くするしかありません。サンプル量は測定機の測定室の容量が約1Lなので、それ以上は入りません。測定時間は平方根(ルート)でしか効いてこないので、5 Bq/kgまで測ろうとすれば4倍の350分かかってしまうのです。依頼者の方は少しでも検出限界の低いところまで測ってほしいので2倍の料金でも5 Bq/kgを希望されますが、必要ない場合には説得をして10 Bq/kgにしてもらったり、場合によっては測定する必要がないということで御断りの説得をすることもあります。
そうしないと、たった1台の測定器では対応しきれませんし、本当に測定しなければならないサンプルが測定できなくなったり、測定が遅れたりしてしまうからです。
5.測定データの公表
依頼分析であっても、データ公開の原則を納得してもらったうえで測定することにしています。すでに、ホームページで産地名とサンプル種別をつけたデータの公開を始めています。1月からは、市販されている食品の抜きうち買い取りサンプリングを行い、その結果を公表するとともに、大手小売業者や自治体(測定機関を有する県や大都市)あるいは市町村への測定体制整備の要請をしていく予定です。もっとも、買取には資金が必要なので限界があり、年間300検体程度の調査をめざしています。
6.自主基準
さて、測定値を私たちはどのように評価すればいいのでしょうか。国の暫定規制値は、飲み水や牛乳、乳製品の200 Bq/kg、それ以外のすべての食品の500 Bq/kgの2種類の基準を示していますが、まったく乱暴です。それに比べてチェルノブイリ事故による放射能で今も苦しんでいるウクライナの基準は、きめ細かです。例えば、ウクライナの2006年設定基準(Bq/kg)は、セシウムCs-137については、パン 20、 ジャガイモ 60、 野菜 40、 果物 70、肉 200、 魚 150、 ミルクと乳製品 100、飲料水 2、卵(1個当たり)6、 幼児食品 40などです。日本政府が無視しているストロンチウムSr-90についての基準もあります。貧しい人々が日常たくさん食べなければならないものについては低い基準が設定されていることがわかります。誰でもたくさん飲まなければならない飲料水は、日本の暫定基準の100分の1です。こうしたウクライナやベラルーシの基準を参考にしながら、私たちの自主基準を計算してみました。厚生省が発表している食品群別平均1日摂取量リストの食品群別に、米や小麦などの主食や野菜類、肉類、魚類は30 Bq/kgとし、イモ類、豆類、菓子類などは50 Bq/kgとしました。幼児食品は一律に20 Bq/kgとしました。この基準と摂取量を掛け算し、国際放射線防護委員会ICRPのCs-137と134の実効線量係数を算術平均したもの(来年は、Cs-134が減衰するので、修正が必要)を掛けて得られた福島由来放射性セシウムによる年間内部被曝線量を示します。政府暫定基準では約7 mSv/年ですが、自主基準では0.35 mSv/年、幼児は0.1 mSv/年以下です。これに測定されていないSr-90や、外食などをして過剰に摂取する分を加えても、0.5 mSv/年程度におさめることが出来ると思われます。カリウムK-40などの天然核種による年間内部被曝線量が0.4 mSvですから、今回の福島事故による食品を経由した過剰被曝が、ほぼそのレベルでコントロールできるということになります。なお、内部被曝を重要視していないICRPの実効線量係数に対する批判があることは承知の上で、過去の基準や天然由来の核種による被曝線量などとの比較のために、あえてこの係数を用いたことをお断りしておきます。
また、この基準であれば飲料水を除けば検出限界を20 Bq/kg以下にすればよく、測定時間が短くて済むだけ多くのサンプルの測定が出来ます。飲料水については家庭用の鍋で5~10倍濃縮をかけてもらってからセンターに送ってもらえば、測定時間の短縮が出来ます。セシウムは450 ℃まで揮散しないとされているので、濃縮は問題ありません。
この自主基準はまだほんのたたき台です。多くの皆さんからのご意見、修正提案を期待しています。全国の皆さんとの討論を経て、非情かつ無責任な政府に暫定基準改正に向けての圧力をかけていきたいものです。また、生産者を守るために、基準超過作物や食品について東京電力に対する損害賠償請求の支援が出来るようになることをめざしたいと思います。
7.汚染地の支援
すでに東北のホットスポット地域で不安の中で暮らしている母子ネットワークから支援要請が来ています。母乳や尿の採取方法、濃縮方法などの検討を進め、100人規模の無償分析をするとともに、問診票調査や空間線量調査なども併せて行い、被曝回避のためのアドヴァイスができることをめざしています。
市町村に測定機の購入を求める運動が各地にあり、ちらほらと購入検討の情報が入ってきています。つい先週も、関東北部のホットスポットの町で測定機購入が決定し、ではどの機種を買おうかということで市役所側から市民側に問い合わせがありました。それに対する回答として、当測定センターが作成した機種選定のための性能比較表を送ったばかりです。このように、支援には様々なものがあり、我々自身が日々の測定を精力的に続ける中から、支援できる事柄が増えていくのではないかと思っています。
8.測定機について
数万円で市販されているガイガー計数管式、あるいはシンチレーション式線量計では食品中放射能を測定することはできません。50万円程度のしっかりしたサーベイメーターでも、せいぜい100Bq/kg以上でなければ測れません。食品業者やお寿司屋さんなどで、この種の測定器を使って食材のチェックをしている場面をTVで見たことがありますが、政府暫定(2011年3月17日〜2012年3月31日まで)基準 500 Bq/kgを超えていないことを確認する程度のことしかできないでしょう。
我々が提案した自主基準のレベルのガンマ線核種(事故直後に大量に放出されたヨウ素I-131が半減期の10倍以上の時間が経過して1000分の1以下に減衰したので、現在測る必要があるのは、Cs-137と134だけです。Sr-90は、ガンマ線を出さないので、測定が難しく、また、別の測定装置が必要ですから、残念ながら対象外です)を測定するためには、ガンマ線のエネルギースペクトルが得られる測定機でなければなりません。感度的にも精度的にも優れているのは、ゲルマニウム半導体核種分析装置ですが、価格が1500万円程度と高く、また、液体窒素で冷却しながら測定しなければならないためにランニングコストがかかります。そこでやむなく、300万円台から500万円程度で市販されているヨウ化ナトリウムNaIシンチレーションスペクトロメーターを購入しました。我々が購入したのは日立アロカメディカル社が販売している装置ですが、製造したのはアメリカのキャンベラ社です。ところが調べてみると、キャンベラ社はすでに世界最大の原子力産業であるアレバ社(仏)に吸収されていました。考えてみれば、日立も原子炉メーカーです。この矛盾に悩みながらも、性能本位での機種選択をしました。何とも皮肉な事態です。
9.財政問題
発足して間もないので、収支バランスもなにも見当がついていない状態です。家賃も電気代(測定機には室温を一定に保つ空調が必要です)も支払っていない居候状態で、ボランティア測定スタッフの交通費くらいは出したいということで検討している最中です。測定機購入費はなんとか寄付金でまかなえそうな形勢ですが、それ以降の測定機の買い増しとか、無償測定のための資金集めはこれからの課題です。別の助成金の申請も検討中です。
最後に、この報告を終えるにあたって、本誌を読まれた方で、東海地方在住の方に、ボランティア測定スタッフへの応募やカンパのお願いをしたいと思います。カンパの振込先は以下の通りです。よろしくお願いします。
★2015年頃の記録(現代技術史研究会報(2015年1月)より)
二つ目の文章は、現代技術史研究会報(2015年1月)に書いた報告です。すでに述べたことと重複もありますが、そのまま貼り付けます。この研究会は1951 年、技術評論家の星野芳郎氏(1922-2007)が都立大学や東京. 大学等々の学生に呼びかけ立ち上げられ、科学技術者の社会的責任を中心に据えた研究会で、70年以上の歴史があります。いわば、人民のための科学技術者たちの集まりです。残念ながら会員の全員が身上の通りに頑張れたかというと、ちょっと物足りない感があります。それでも、元原発技術者として発言を続ける後藤政志さんや、物性物理学者の井野博満さんはこの会の会員で、原子力市民委員会のメンバーでもあります。
市民放射能測定センター・Cラボの3年間と今後
1.はじめに
福島原発事故発生以来もうじき4年が経過しようとしています。現代技術史研究会員諸兄は、今こそ「人民のための科学技術者」ここにありと、様々な現場で蓄積してきた技術や知識をフル動員して頑張っておられることと思います。かくいう小生も、非力ながら原子力市民委員会において脱原子力政策大綱「原発ゼロ社会への道」(www.ccnejapan.com/)の制作に参加し、東海地方における脱原発運動ネットワークである「未来につなげる東海ネット」運営委員として活動しています。さらに、この東海ネットの作業部会として発足した市民放射能測定センター(略称Cラボ)の立ち上げから関わって、食品や土壌中の放射能含有量の測定を行ってきました。今回は、そのCラボの3年間で経験したことや今後の課題などについて報告したいと思います。(Cラボの活動については2013年5月19日の現技例会でお話ししていますが、今回改めて整理した形で報告したいと思います。)
2.測定器の選定と購入
愛知県は東三河地方で少々の放射性物質の降下があって数百 Bq/kgの茶の汚染がありましたが、名古屋ではほとんど観測されませんでした。しかし、子育て中の若い母親を中心にして学校や保育園給食の放射能測定を求める声が高まりました。また、東北や関東産の有機農産物を扱う産直ネットワークを営む人々にとっては深刻な事態で、消費者保護のための食品測定と、生産者支援のための土壌や農産物の測定が急務となっていました。
こうした人々の声と熱意が市民放射能測定センター開設へとつながっていったのですが、さてどのような測定器を買うべきかということで当時市販されていた5機種の性能比較を行い、日立アロカメディカル社製CAN-OSP-NaIを購入しました。皮肉なことに、日立はまさに原子力産業の一角であり、この装置を開発したキャンベラ社(米国)はすでにフランスの国策原子力産業アレヴァ社に買収されていました。それでもこの機種を選定したのは、ソフトウェアの良さと納期の短さで、当時他のメーカーでは半年待ちだったのに対して、わずかに1か月で納品されました。価格はベラルーシ製のATOMTEXの約130万円と比べると約500万円と高額でしたが、今になってみて当時の判断は的確であったと思っています。購入費用も市民から寄せられたカンパと高木仁三郎市民科学基金からの助成金でクリアすることが出来ました。
この時作成した性能比較表は、その後も大いに役立ちました。母親グループが一宮市に給食測定用に放射能測定器の購入を求めた時、市側が購入しようとした装置の性能が不十分なものであることを明らかにして、購入予定を変えさせたり、北名古屋市や那須塩原市の測定器購入のアドヴァイスをしたりすることも出来ました。
3.ボランティア測定者養成講座
かくして測定器が2011年7月に届いてすぐに測定が始まりました。測定を担当するのはボランティア測定者養成講座を受講していただいた方々で、理科系の知識の有無を問いません。
放射線放射能の基礎知識を約3時間の座学で学んでいただいてから、測定実習をしていただいています。これまで15回の研修会を行い、修了者は約200人です。その中から数十人の方々が測定者となって頑張っていただき、様々な都合があって抜けられる方もいて、現在シフトに入って下さっている方は約10名です。歩留まりは良くないのですが、啓発講座だと思えばとても有効な働きをしてきたと思っています。また、この中には30才代、40才代の優秀なメンバーがいて、福島原発事故発生で唯一良かったことだと思っています。
4.測定結果の直接的効果
この3年間の測定件数は約2500検体です。学校や幼稚園の給食食材を母親たちが苦心して入手してきて、汚染食品の使用を未然に防いだことが数回ありました。すでに園児が食べてしまった椎茸から高濃度の放射能が検出されて、行政や幼稚園を動かすことになりました。また、この事件を契機に愛知県私立幼稚園連盟加盟幼稚園の陰膳調査が始まり、年間150検体の測定を行っています。
名古屋のホームセンターで売られていた腐葉土から2万 Bq/kg超が検出されて、愛知県に回収指示を出させました。
岩手県全土316地点の土壌汚染調査を行って、県南部の2市2町の深刻な汚染状況を明らかにし、また、2011年3月20日から4月にかけて大量のヨウ素131(173万 Bq/m2)や放射性セシウム(33万 Bq/m2)の降下があったことを推定し、岩手県に健康調査の必要性を提言しました。
5.検出限界を下げる
分解能に限界があるNaIシンチレーターで大した測定が行えるわけがないと放射線の専門家の多くが思っているようですが、全国の市民放射能測定所は懸命にその限界性を突破して、素晴らしい測定をし始めています。
測定器に付属している鉛の遮蔽(30~50mm)では不足なので、さらにほぼ同量の鉛遮蔽を買い足したり、水を満たしたペットボトルが6本入った段ボールを測定器の周りに壁状に張り巡らせたりしてバックグラウンドを大幅に下げることによって、検出限界は大幅に下がりました。電源安定化装置の導入や厳格な室温のコントロールなども加えて、検出限界が1 Bq/kgを下回る測定に成功しているところもあります(ゲルマニウム半導体検出器で確認済み)。測定時間の大幅短縮にも成功しています。
測定器メーカーを動かして、検出効率を上げるためにマリネリ容器が使えるようなソフトの改造をさせたり、そのマリネリ容器にサンプルを半量つめた状態でも測定が出来るように効率校正をさせたりすることにも成功しています。
6.みんなのデータサイト
高木仁三郎市民科学基金に測定機購入のための助成金申請が殺到したことから、助成金不足を補うために市民測定所測定技術交流研修会(年に3回)が行われるようになり、測定上の問題点の克服、相互援助が出来るようになりました。また、この研修会をきっかけとして、共同の検索サイト「みんなのデータサイト」(https://www.minnanods.net/)が構築されました。現在、市民測定所が測定した約1万の食品データの検索ができるようになっています。参加測定所数は現状で21ですが、参加準備中の測定所が数か所あります。参加するためには、Cラボが福島産汚染玄米をベースにして作製した基準玄米セットの測定を行い、En数精度検定に合格する必要があります。この精度検定で様々な不具合や問題点が明らかになり、その解決のためにCラボなど先進的な測定所が応援したり、測定器メーカーへの様々な要求が可能になっています。
その中で、応用光研製測定器の解析ソフトの不具合が発見されました。10 Bq/kg以下になると、Cs-134とCs-137の比率が逆転してしまうなど測定値が不安定です。「そもそも10 Bq/kg以下の測定を想定していない」などと居直る同社に対して、手紙や電話の応酬ではらちがあかず、この測定器のユーザーとみんなのデータサイトの主要メンバーが揃って応用光研を直接に訪問しました。すると意外にも、同社は冒頭からソフトの根本的改造に着手したことを明らかにしたのでした。
このような他機種の不具合の分析をしてみて、Cラボの機種選択が成功だったと感じています。ゲルマニウム半導体核種分析装置に積んでいたソフトを使っているところがポイントです。
7.今後の課題
福島事故の衝撃の風化とともに測定依頼は激減し、全国100余か所の市民測定所にとっては正念場を迎えつつあります。測定料収入でやりくりする財政基盤ではやりぬけません。Cラボでは、早くから福島など汚染地域からのサンプルは無料で測定し、汚染地を支援するための土壌調査や生活空間調査なども無料で対応してきました。それを支えるのは、ボランティア測定者の存在とカンパと助成金です。
国も自治体も、汚染を放置し、きちんとした土壌汚染調査をしようとしていません。そのため、「みんなのデータサイト」では、首都圏や北関東、宮城山形などできちんとした標準サンプリング方法を定めて、土壌調査プロジェクトを展開することにしました。現技会員諸兄でこの調査にご協力いただける方は大沼(nw4j-oonm★asahi-net.or.jp ★を@に変更してください)までご一報ください。
★そして今(2015年から2021年までの記録)
この報告を書いてからさらに5年間が過ぎました。依頼検体はさらに激減しています。開設当初は毎日測定が行われていましたが(土日測定は主に現役サラリーマンの担当でした)、Cラボの営業日も週に3日になりました。
1.2回の引っ越し
Cラボはこれまでに2回引っ越しをしています。最初の4年間を家賃なし、水道光熱費なしの居候をさせてくれた産直会社「生活クラブ」を出て、家賃無料の民間マンションに引っ越しました。食品中放射能10 Bq/kg以下なら食べるべきだと明言してほしいとの産直会社の要望に応えなかったことが引っ越しの最大の理由でした。この頃、食品基準をめぐる激論があったのです。食べる食べないの判断、すなわちリスクコントロールは、正しい測定値と必要な情報に基づいて、個人が行うべきだというのがCラボの見解でした。
追加の遮蔽体を入れて合計250 kgの測定器の引っ越しをどこに依頼するかであれこれ検討したのですが、奈良から来てくださっているボランティアの方がユニック(クレーン)付きのダンプカーを持ってきて、いとも簡単に運んでくれました。Cラボにはいつもこういう幸運が付きまとっているようです。
引っ越し先の民間マンションでは追加遮蔽のさらなる強化が必要になりました。壁や天井から天然核種由来のガンマ線が飛んできて、空間線量率が0.1 µSv/hを超えるのです。コンクリートの骨材である砂や小石にトリウムやウランと娘核種が含まれているものと思われます。5 mmの鉄板を2枚重ね、測定器の周りには2L入りペットボトル6本が入った段ボールを積み上げて、遮蔽体の合計は約500 kgになりました。さらなる問題は、隣家の住人が「放射能測定センター」の看板を見て管理組合に訴えたことから発生しました。マンション管理規定では、居住以外の利用が禁止されていたのです。暴力団などの居住を防ぐために、多くのマンションではこういう管理規定を作るようになっていたのです。このためわずか半年後には2度目の引っ越しをすることになってしまいました。
引っ越し先を探してあちこちに行きました。外国人労働者や日雇い労働者の人権保護などに境内を提供している徳林寺では、スペースを無料で貸すから自分たちで建てなさいというアドヴァイスもいただきました。結局最後は、日本聖公会・聖ヨハネ教会の旧牧師館を貸していただけることになりました。耐震診断で低評価だったために牧師さんが引っ越してしまった後の空き家です。1級建築士の方の計算とご指導をいただいて、測定室スペースの耐震強化工事を自力で行いました。木製のサッシがはめられている古式騒然たる5DKの2階建て戸建て住宅ですが、なかなか快適です。前庭では畑ができます。周辺は閑静な住宅街です。測定器の移動では、またしても奈良からユニック付きのダンプカーの出動をお願いしました。
2.みんなのデータサイト結成
結成に参加した「みんなのデータサイト」が発展して、最大34測定所が参加する大所帯になりました。Cラボの活動とも密接な関係があります。みんなのデータサイトのデータベースに一気にデータをアップするためのCSV入力システムを作ったのがCラボの渡辺極之さんでした。Cラボが作製した基準玄米が、みんなのデータサイト参加測定所の精度管理の根幹になりました。
すでに述べたように、17都県土壌放射能調査にあたっては、Cラボが2012年から1年がかりで岩手県全県316地点で行った土壌汚染調査で開発した調査方法が採用されました。岩手県の調査は、2011年5月に大沼&大沼で岩手県の津波被害地のボランティア活動に出かけて、放射線放射能について岩手宮城の各地で勉強会を開催して歩いた時に知り合った人脈が実った調査活動でした。
3.ホットスポットファインダー(HSF)購入
HSF購入は初年度にNaIシンチレーターを購入(500万円)して以来の高額出費(15%引きの市民運動価格で税込み147万円)でした。Cラボ内でカンパを募り購入を決めました。すでにこども未来測定所や希望の砦測定所が保有している装置で、GPSを搭載しGoogle Earth上に空間線量率を自動的に記録してくれる優れものです。
まだその能力を十二分に活用できているとはいいがたい現状ですが、以下に述べる避難者訴訟原告の皆さんの避難元汚染調査、郡山市の有機農家の支援、伊藤延吉さんと協同した飯館村調査、伊達市の汚染調査などで活用できています。
4.避難者損害賠償訴訟愛知・岐阜の支援
愛知県にも1000人を超える原発事故の避難者の方がいらっしゃり、愛知県以西では最大数です。岐阜県への避難者と合わせて、その中から200数十人の方達が損害賠償訴訟で東電と国を告発しました。一審は国の責任を認めないなど本当に不当判決でした。弁護団が被曝による健康被害リスクをほとんど主張しなかった裁判で、原告の方々には大きな不満が残りました。上告して名古屋高裁に上がった段階で7家族の方々が別の弁護団のもとに裁判を闘うことになりました。「だまっちゃおれん訴訟」と名乗っています。このため、きちんとした避難元の汚染調査が必要となり、HSFを引っ提げて福島県に遠征し、避難元住宅や道路などの汚染地図を作成し、土壌サンプリングと測定も行って、裁判所に証拠資料として提出しました。
南相馬市では事故後わずかに1年で避難指示解除された住宅の玄関先の土壌で、事故後9年を経ても8000 Bq/kgを超え、放射線管理区域基準(4万 Bq/m2)の10倍を超える深刻な汚染を発見しました。
この訴訟のキックオフイベントなどでは、原告の方々のうちWi-Fi環境が良くない方々のために、Cラボが発信ステーションになったり、法廷の傍聴活動にCラボメンバーが参加したりしています。
5.郡山の有機農家支援
Cラボ発足当時にお世話になった産直会社の農産物生産者の一人だった郡山市の有機農家とのご縁が続いています。
2013年から毎年6月に数人で1週間前後泊まり込みの滞在をしながら、援農や農家の屋内や庭及び農地の汚染マップ作成、同時に作物や土壌の経年的な測定を続けています。屋内で最も線量が高かったのは大きな囲炉裏で、原因は汚染した炭や薪を燃やしたことでした。これについては、岐阜県の汚染していない木灰を送って入れ替え作業を行いました。
この農家がある集落で開かれている農産物直売所では、2020年時点で数万 Bq/kgの木灰がワラビのあく抜き用に販売されているのを発見して、販売をやめていただいたりしました。縁故品で持ち込まれた100 Bq/kg超のイノシシ肉も発見して、食べるのをやめてもらいました。
6.おわりに
さて、Cラボの今後の10年はどうなるのでしょうか。Cs-137の半減期である30年頑張るとすると、今後20年ということになりますが、とりあえず10年です。資金的には何とかやれそうです。年に1~2回発行している「Cラボニュース」を送ると、カンパが贈られてきます。過去の蓄積も少々あります。最も心配なのはメンバーの加齢でしょう。これを書いている筆者は現在76歳ですから、10年後は86歳になっていることになります。幸いボランティアスタッフの主力は筆者より10歳ほど若いし、さらに10歳若いメンバーもいます。安く貸していただいている日本聖公会の聖ヨハネ教会の信者さんの主力が高齢であることも少し心配です。
ともかく、みんなのデータサイト参加の全国の測定所の皆さんとともに、市民による放射能測定活動を続けていきたいと思います。