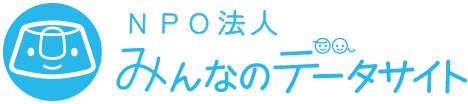はかるならの歩みとこれから
(1)はじめに
「はかるなら」は開所以来、丸8年になります。会員番号は220を超えていますが、退会や未更新がありますので、実質の登録会員は100名前後になっています。とりわけ昨年4月からはコロナ禍のため休業を余儀なくされ、各種イベントを中止していますので、測定所の運営自体も寂しくなっています。ただ開所日(毎週木・日曜日)には少数の測定スタッフによる測定を継続し、測定結果や情報を会員MLやホームページ・ブログで発信しています。
(2)開設への歩み
奈良・市民放射能測定所は2013年3月に発足しました。その前史には子育て真最中のお母さん方の子供たちの給食の安全を求める運動がありました。行政との度重なる話し合いや議会への請願書提出など精力的な取り組みがなされました。その中で、どうしても国の「基準値」を超えることができない行政任せではなく、「やっぱり市民測定所が必要だね」という機運が高まり、2012年3月に準備会が始まりました。
すでに2012年5月に開設されていた京都・市民放射能測定所の仲間から、放射能測定のイロハから測定所開設のノウハウまで、熱いサポートを受けました。
低線量・内部被ばくのリスクに警鐘を鳴らしていた医療問題研究会の医師から、他の測定所も羨む広さのある交通至便な開設場所の提供を受け、準備会メンバーの開設に向けた意欲は飛躍的に高まりました。
現役で化学分析の仕事に携わっておられる方や放射能測定の専門家も馳せ参じてくれました。市民から会員登録・開設資金の協力も少しずつ集まり始めました。
準備会活動に1年間も要した“産みの苦しみ”の諸々を省き、概略記述になりましたが、上記のような取り組みを経て、ようやく開設の運びになりました。
(3)測定の継続が基本
原発事故から10年が経つとはいえ、半減期が30年もあるCs-137はまだ約8割も残存しています。私たちのかけがえのない命を育む水・空気・土壌・食品は汚染され、誰もが総被ばく時代に生きることを余儀なくされています。国の基準値「一般食品100Bq/kg」は、国と東電の責任を免罪する数値であって、断じて国民の命・健康を守るためのものではありません。市民自らが放射能を測定し、被ばくの知識を身に着け、正しく判断することが必要です。目に見えない放射能を測定し、可視化してゆくことは、国や行政任せの状況から、自分や家族の生活・健康は自分で守るという自立した生活を作ってゆく大きな一歩になります。放射能汚染に関わる情報発信だけではなく、自分の人生は自分で切り開くのだという当たり前の感覚を取り戻すことに繋がります。それが国や行政の在り方を変えてゆく力にもなると考えています。
小学校で使用されていた園芸用培養土が汚染(「基準値」未満)されていたことがあり、早速、担当教育委員会に申し入れ、改善を約束してもらいました。奈良県産の椎茸から放射性セシウムが検出(「基準値」未満)された時、生産者との話し合いは実現しませんでしたが、1年後の測定では不検出に改善されていることが判明した事例もありました。
1950~1960年代の核実験やチェルノブイリ事故による汚染が相当数の測定で判明し、測定所を開設していなければ実感しえなかった真実を驚きとともに再認識しました。
一般市民の放射能に対する感覚が薄れつつあるとはいえ、政府による「復興」に名を借りた放射線安全神話の拡大、強制帰還、汚染土壌の「再利用」、汚染水の海洋投棄など放射能汚染は拡大されています。継続的測定による線量変化の把握も含めて、“はかって安心!知ってなっとく!”をめざす測定所の役割は依然として大きいものがあります。
会員数や検体の持ち込み数の減少は避けがたい現象ですが、全国の市民測定所の仲間と励まし合いながら、測定を基本とした活動を継続したいと思います。
(4)交流の場としての役割
測定所は単に測定するだけの場所ではありません。相談センター・情報センターの機能もあわせ持っています。誰もが気軽に立ち寄り、子育てや安全な暮らしのための情報を交換したり、安全な食品を購入できたりするような交流の場として機能することが必要です。私たちは、講演会・無料測定まつり・学習会などに加え、避難者交流会(ツキイチ・カフェ)やおしゃべりランチを適宜開催してきました。
測定所を気軽に立ち寄れる、親しみやすい場所にするために、2018年8月から名称をはかるなら(奈良・市民放射能測定所)に変えました。新しい素敵なロゴもできました(添付参照)。
そんな中で安定ヨウ素剤の配布を求める市民の強い要望を知り、スタッフの医師の協力で、過去2回の配布会を実現しました。
コロナ禍が収束すればいっそう充実した交流を実現してゆきたいと考えています。
(5)測定精度の充実と拡大
時間の経過とともにシンチレーターではますます低線量の測定が困難になっています。西日本市民ネットワーク(京都・大阪・兵庫・滋賀・広島・奈良の測定所)では2・3ケ月に一度会合を開き、交流を深めていますが、ゲルマニウム半導体検出器を保有する測定所の好意で、判断に迷うような検体のクロスチェックが実現しています。また、「魚測定プロジェクト」と称して、各測定所持ち回りで海産物を取
り寄せ、ゲルマ器での測定を行っています(現状はコロナ禍のため頓挫しています)。
通常運転原発からのトリチウムの放出量は、西日本では多数を占める加圧水型原発の方が沸騰水型原発よりも多いことが報告されています。汚染水の海洋投棄の問題も含めて、トリチウムなどベータ線の測定の必要性が高まっています。
たらちね(いわき放射能市民測定室)ではベータ線の測定も行われていますが、今後10年を見通す時、みんなのデータサイトとしては放射能の減衰状況に対応したゲルマ器の測定強化とともに、トリチウムやストロンチウムなどのベータ線測定にも活動を広げることが重要であると思われます。